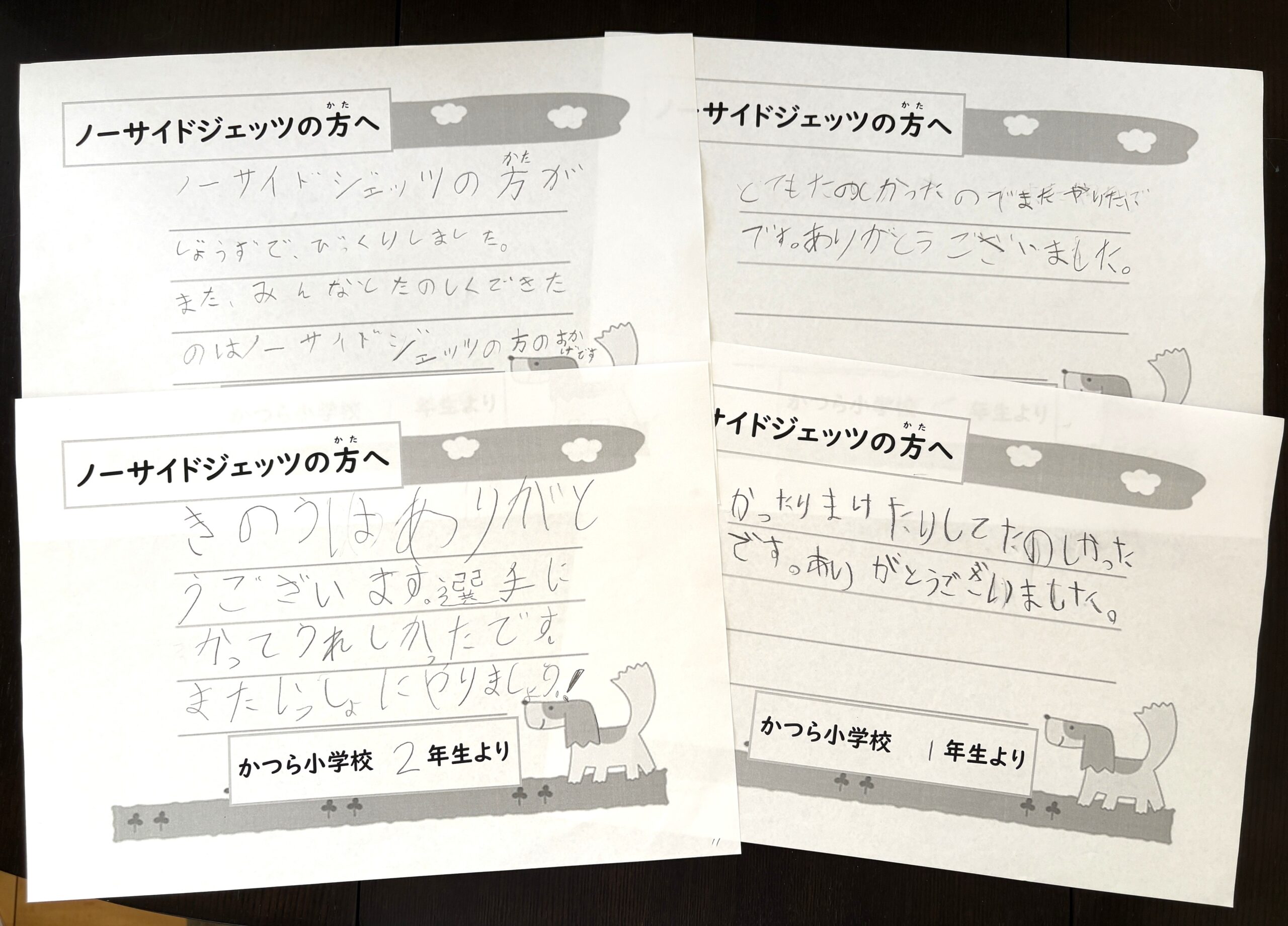映画『フロントライン』に重ねた記憶。コロナ禍の福祉現場、もう一つの「最前線」で私たちが向き合ったもの

こんにちは アンドナの野村です。
先日、映画『フロントライン』を観ました。
2020年2月、新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船が横浜港に入港。未知のウイルスに対する不安と恐怖の中、様々な葛藤を抱えながらも懸命に人命救助にあたった災害派遣医療チーム「DMAT」の記録です。
スクリーンに映し出されたのは、防護服に身を包み、見えないウイルスに立ち向かう医療従事者の姿、そして刻一刻と変化する状況を伝えようと奔走するジャーナリストたちの姿。
観ているうちに、私はいつの間にか、数年前に自分が立っていた場所の記憶を鮮明に思い出していました。
あの時、誰もがそれぞれの「最前線」で戦っていた
映画を観て、一つの実感が胸に突き刺さりました。それは、「あの時、多くの人が、多くの場所で、見えない敵と戦っていたのだ」ということです。
メディアで連日報道されたのは、医療現場の逼迫した状況でした。もちろん、そこが闘いの中心であったことは間違いありません。しかし、私たちの社会には、カメラには映らない無数の「最前線」が存在していました。
そして、私にとっての最前線は、当時働いていた障がい者福祉施設でした。
コロナ禍の福祉現場。静かだけれど、熾烈な闘い
私が当時働いていたのは、重度の身体障がいのある方たちが通所する施設です。
そこは、利用者さんにとって社会とつながるための大切な場所であり、ご家族にとっては生活を支える上でなくてはならない場所でした。
緊急事態宣言が発令され、社会全体が活動を自粛する中でも、私たちの施設は決して扉を閉ざすことはできませんでした。
なぜなら、そこでのケアがなければ、日々の生活そのものが成り立たなくなる方々がいたからです。
食事、入浴、排泄の介助。そのどれもが、利用者さんの身体に密着して行われます。ソーシャルディスタンスなど、そこには存在しません。「もし一人でも感染者が出たら、同じフロアにいる全員が濃厚接触者になる」。私たちは常にその恐怖と隣り合わせでした。
そして、恐れていた事態が起こります。施設は、やむを得ず一時閉鎖に追い込まれました。
しかし、利用者さんの生活は一日たりとも止まりません。
私たちはすぐに体制を切り替え、防護服に身を包み、利用者さんのご自宅を一軒一軒訪問しての支援を続けました。
もちろん全ての利用者さんのお宅を訪問することはできないため、協力をお願いしてぐっと我慢してくれたご家族もたくさんいらっしゃいました。
当初は、誰もが不安の淵にいました。
「この先、うちの子はどうなるの?」と訴えるご家族の声。
「もし自分がウイルスを家に持ち帰ったら…」と、自身の家族への影響に葛藤するスタッフの声。
しかし、その不安と恐怖が、いつしか私たちを一つのチームに変えていったのです。
「この状況を、みんなで乗り越えるしかない」。利用者さん、ご家族、そしてスタッフが、それぞれの立場で協力し合い、支え合う関係がそこには生まれていました。
特に、重度の身体障がいのある方にとって、コロナへの罹患は「死」の恐怖と直結していました。たとえ感染しても、専門的な介助ができるスタッフがいなければ、病院で入院生活を送ることさえ困難な現実があったからです。
今思い返してみても、あの時の、スタッフ、利用者さんとご家族の協力体制は、本当に素晴らしく、「これこそが福祉のチーム力だ」と心から感じるほど強固なものでした。
普段、施設にはご家族から様々なご要望が寄せられます。「帰宅時間を変えてほしい」「この日も通所できないか」—。もちろん、できる限りお応えしたいのですが、人員体制の都合などでお断りせざるを得ないこともあり、まさに、押し寄せるご要望と向き合う日々です。
しかし、あの緊急事態の中では、状況が全く異なりました。
最初こそ戸惑いや不安をぶつけられたご家族もいらっしゃいましたが、すぐに自分たちの置かれている立場を理解し、自分のことだけでなく施設に関わる皆のことを考え、一致団結してこの危機を乗り越えよう、という協力体制を築いてくださったのです。
それはまさに、「支援する側」と「される側」という垣根を越え、共に戦う「同志」として気持ちが一つになった瞬間でした。
この経験は、私にとって非常に大きな財産となりました。
普段は立場の違いから様々な意見が交わされる関係性も、いざという時には一致団結できる。障がい福祉サービスは、単なる事業ではなく、地域で「ともに生きていく」ための営みなのだと、改めて強く感じました。
この経験がなければ、アンドナを立ち上げるという決意には至らなかったと、今でも思います。それほど、私に強い衝撃を与えた出来事だったのです。
支え合う社会の姿を、映画は思い出させてくれた
映画を観て、もう一つ、改めて思い出したことがあります。それは、あの過酷な状況下で、重度の障がいのある方々の暮らしを支えていたのは、私たち施設スタッフだけではなかった、という事実です。
日々変化する状況について的確な情報をくださった市役所の方々。施設の開所を維持するために動いてくださった保健所の方々。そして、「福祉の現場で使ってください」と、貴重なマスクや消毒液を届けてくださった地域の方々。
ご自身も不安なはずなのに、誰かのためにと行動してくれた多くの人々に、私たちは確かに支えられていました。映画『フロントライン』は、最前線で戦う人々の姿を通して、その背後にあった無数の善意や連帯の存在をも、私に思い出させてくれました。
「誰一人取り残さない」社会のために
映画『フロントライン』は、改めて私たちに問いかけてきます。「困難の最前線とは、どこなのか。本当に支えを必要としているのは、誰なのか」と。
コロナ禍という未曾有の危機は、社会の脆弱な部分を浮き彫りにしました。
障がいのある方々やそのご家族、そして彼らを支える福祉の現場は、平時でさえ多くの課題を抱えています。危機的状況においては、その困難がさらに増幅されるという現実を、私たちは身をもって体験しました。
私たちアンドナは、「誰もが、ありのままで、笑顔で暮らせる社会」を目指しています。
このコロナ禍での経験は、その思いを一層強いものにしました。困難な状況にある時こそ、手を差し伸べ、寄り添う存在が必要です。一人ひとりの「当たり前の日常」を守ることが、社会全体の豊かさにつながると信じているからです。
映画『フロントライン』が記録したジャーナリストたちの闘いも、私たちが福祉現場で向き合った日々も、根底にある思いは同じなのかもしれません。それは、「目の前にいる、守るべき誰かのために」という、ささやかだけれど、何よりも強い光です。
この光を、そして私たちを支えてくれた多くの光を、これからも大切に灯し続けていきたいと思います。